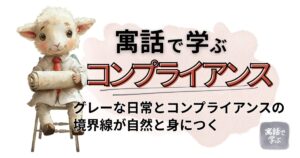【寓話で学ぶガバナンス】シリーズとは?
森の仲間たちが経営する「モリモリ商会」を舞台に、フクロウ監査役と共に“会社の気になること”を考えていくシリーズです。ガバナンスの知識を、物語のようにやさしく学べる内容です。
――この森の奥で、モリモリ商会が創業したのは、もう10年も前のこと。
今日もフクロウ監査役が、会社のあちこちで起こる“気になること”を見つけては、そっと耳をすませています。
 カメ副社長
カメ副社長……異論は、ないようですね
取締役会の会議室に、カメ副社長のゆっくりとした声が響いた。
その日、経営方針の転換に関する議題が上程されていたが、会議ではほとんど議論がなかった。みんなうなずくだけで、誰も深く意見を述べなかったのだ。
会議が終わると、カメ副社長はウサギ常務を手招きした。



ちょっと、あとで話そうか
その様子を、フクロウ監査役は黙って見つめていた。



“あとで”って、会議で言えなかったことを話すんですか?
新任のリス取締役が、会議後にそっとフクロウ監査役に声をかけた。



どうして、あんなに重要な話なのに誰も発言しないんでしょう
フクロウ監査役は、静かに答えた。



“あとで話そう”が続く組織では、会議が“通過儀礼”になることがある。
本当の意思決定は、別室で行われるようになってしまうのだ
数日後、リス取締役は思い切ってカメ副社長に提案した。



次回は、“あとで”じゃなくて、会議の場で率直に話してみませんか?
カメ副社長は、少し驚いたような顔をしてから、ゆっくりとうなずいた。



……そうだね。君の言うとおりかもしれない
次回の取締役会では、カメ副社長が自ら意見を述べ、ウサギ常務も続いた。会議には、初めて活発な議論が生まれた。
フクロウ監査役は、静かに見守りながら、心の中でつぶやいた。



会議は、あとで話す場ではなく、“今”話すためにあるのだ
「会議外の声」が意思決定を歪める
取締役会や経営会議では、一見するとスムーズに議事が進んでいるように見えても、その背後で“表に出ない力”が働いていることがあります。
特に、「会議では沈黙→会議後に発言」という行動パターンが常態化している場合、それは個人の性格ではなく、組織のガバナンス上のリスクです。
会議外での発言は、議事録に残らず、責任の所在が曖昧になるため、後のトラブルの温床になりかねません。
「本音は別室で」のような文化が続けば、公式の意思決定プロセスが形骸化し、会議体の信頼性を損ないます。
本来、会議は異なる意見が交差し、検証されることで、意思決定の質を高める場であるべきです。
監査役や社外役員は、「発言しないこと」や「会議外でのやりとり」が常態化していないかに目を配り、健全な意思決定プロセスを守る役割を担っています。